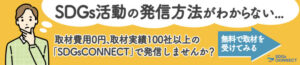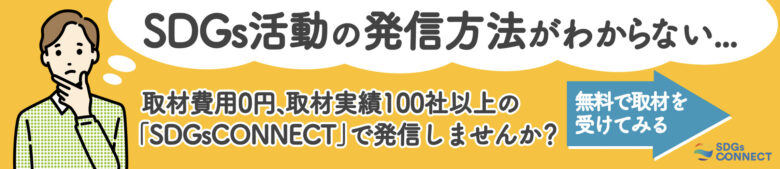【更新日:2023年10月11日 by 田所莉沙】
みなさんはSDGs8「働きがいも経済成長も」について知っていますか。
働きがいを感じながら働くことで、心の健康を維持することができます。それと同時に、私たちが豊かな生活を送るためには経済成長していくことも重要です。
今回はSDGs8の現状に加え、解決策や取り組み事例を分かりやすく紹介します。
| 【この記事で分かること】 |
見出し
SDGs8「働きがいも経済成長も」とは
SDGs8「働きがいも経済成長も」の内容や求められる理由、ターゲットについて紹介します。
簡単に解説-SDGs8「働きがいも経済成長も」の意味や内容
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」は、経済成長と働きがいのある雇用を両立させ、すべての人々が生き生きとした生活を送れるようにすることを目指した目標です。
世界には、貧困や格差、差別などさまざまな理由によって、働きがいのある雇用を得られない人々が数多くいます。また、労働環境の悪化や気候変動の影響で、働きがいを失う人々も増えています。
SDGs目標8ではこれらの問題を解決し、すべての人々が働きがいのある雇用を得られる社会を実現することを目指しています。
なぜ目標8の達成が必要なのか
SDGsの目標8を達成することは、世界中の人々が持続可能な生活を送るために非常に重要です。経済成長が続かなければ社会の維持や発展は難しく、貧困が拡大する可能性があります。
また、働きがいのある労働環境を確保することで労働者のモチベーションが向上し、企業の生産性も上がります。それにより、経済全体の活性化につながります。
さらに、途上国での児童労働や貧困状態にある労働者の権利を守ることなど、人権問題にも深く関わっているのです。
SDGs8「働きがいも経済成長も」のターゲット
SDGs目標8には、人間らしい雇用の促進を目指して、12個のターゲットが設けられています。ターゲットの詳しい内容は、次の通りです。
| 8.1 | ・世界のそれぞれの国で、経済的に豊かになれるようにする。 ・発展途上国や遅れている国においては、毎年少なくとも年間7%の国内総生産(GDP)成長率を保てるようにする。 ※国内総生産(GDP)…国内で一定期間内に生産されたお金やサービスなどの合計を表したもの。 |
| 8.2 | ・商品やサービスに携わっている企業や、労働集約型の産業を中心に経済の生産性をあげる。 ・多様性、技術の向上、イノベーションを通じて、経済の生産性をあげる。 |
| 8.3 | ・働きがいのある人間らしい仕事を増やしたり、会社を始めたりと、新しいことを始めるための政策をすすめる。 ・とくに中小規模の会社への設立や成長を支援する。 |
| 8.4 | ・2030年までに消費と生産において、世界が効率よく資源を使用できるようにしていく。 ・先進国が主導しながら、「持続可能な消費と生産に関する10ヵ年計画枠組」にしたがって経済成長が発展していくようにする。 |
| 8.5 | ・2030年までに若い人たちや障害のある人たちが、働きがいのある人間らしい仕事をできるようにする。 ・男性も女性も同じ仕事に対しては、同じだけの給料が支払われるようにする。 |
| 8.6 | ・2020年までに仕事も通学もせず、職業訓練も受けていない若い人たちの数を大きく減らす。 |
| 8.7 | ・奴隷のように働かさせることや、人を売り買いすることを終わらせる。 ・むりやり働かせることを終わらせるために、効果的な取り組みを行う。 ・子どもを兵士にすることを含めた児童労働を確実に禁止し、なくす。 ・2050年までにあらゆる形の児童労働をなくす。 |
| 8.8 | ・他の国に移住して働いている人や女性、仕事を続けられるか不安定な状況で働いている人を含めた、すべての人の働く権利を守る。 ・すべての人が安全に安心して仕事ができる環境を整えていく。 |
| 8.9 | ・2030年までに地方の文化や産品を広める。 ・働く場所を作りだす持続可能な観光業を行うために、政策をつくり、実施していく。 |
| 8.10 | ・国内の金融機関の能力を強化し、すべての人たちが銀行や保険などのお金に関するサービスを使えるようにする。 |
| 8.a | ・拡大結合フレームワーク(EIF)などを通して、貿易のための援助を増やす。 ・発展途上国やとくに開発が遅れている国に対して、貿易のための援助を増やす。 ※拡大結合フレームワーク(EIF)…発展途上国の中でもとくに発達が遅れている国々に対して、貿易に関する支援を行う国際的な枠組みのこと。 |
| 8.b | ・2020年までに若い人たちについての世界的な戦略をつくって、実行する。 |
以上のように、SDGs8はすべてのを対象とし、経済成長と働きがいを両立させることを目指しています。
働きがいと経済成長に関する世界の現状と問題
働きがいと経済成長に関する世界の現状と問題について詳しく紹介します。
高所得国と低所得国の雇用状況の差が広がっている
現在、高所得国と低所得国の雇用格差が広がっています。
2023年のILO(国際労働機関)の調査によると、低所得国の労働需要不足率は21.5%と最も高く、続く中所得国はわずかに下回って11%でした。一方で、高所得国は8.2%と最も低いことがわかりました。このことから、低所得の国であればあるほど雇用されにくいという現状があります。
また、国際労働機関は基礎年金受給率と国の平均所得について調査しており、低所得国は高所得国に比べて年金をもらっていない人の割合が多いことがわかりました。このことから、世界的な労働需要不足を減らすために、所得投資を拡大することが必要です。
▼参考
危機が連鎖し増幅 広がる雇用格差
途上国では児童労働が当たり前になっている
途上国では貧しい家計を支えるために児童労働が見過ごされる傾向があります。児童労働によって、子ども達は肉体労働を迫られており、中には教育を受けられない人もいます。2020年時点で約1億6,000万人の児童労働者がいます。この問題に対する解決策として、法制度の整備や教育機会の提供、家庭の経済状況の改善などが挙げられます。
児童労働を利用した商品やサービスの利用を避けるなど、私たちも日常生活の中でできることがあります。
▼参考
児童労働 | 子どもの保護 | ユニセフの主な活動分野
男女のジェンダー格差が残っている
SDGs8では全ての労働者が公平な就労機会を持つことを目標としており、労働におけるジェンダー格差の解消も含まれています。
世界各地で男女間の賃金格差や昇進格差、就業機会の格差が見られます。国際労働機関の報告によれば、女性の労働者は男性に比べて低賃金の仕事に就く可能性が高く、またフルタイムで働く女性の賃金は男性に比べて平均で20%低いとされています。
これは日本でも問題になており、女性管理職や女性政治家が少ないといった問題が挙げられます。
働きがいと経済成長に関する日本の現状と問題
働きがいと経済成長に関する日本の現状と問題について詳しく紹介します。
残業時間の長さと過労死が社会問題となっている
日本では、長時間労働や過労死が深刻な社会問題となっています。英語では「Karoshi」と表現されており、その深刻さが理解できます。過労死の基準は以下の通りです。
|
労働環境の改善が求められていますが、その背後には働き方への認識の問題が潜んでいます。労働者自身が長時間労働を「働きがい」や「責任感」の表れと捉えてしまう風潮が、この問題の解決を難しくしています。
そのため、SDGs8達成のために社会全体の制度改革や企業の労働環境改善が大切です。
▼関連記事
働き方改革の目的を知り企業価値を高める!具体的な取り組みと効果とは
▼参考
ベリーベスト法律事務所
非正規雇用が増加し、賃金格差が生じている
日本では近年、非正規雇用が増加しています。2022年には2,101万人もの非正規雇用者がいます。その原因として働き方改革の影響や企業側の人件費削減などが挙げられます。企業は人件費削減を求めた結果、人件費の安い非正規雇用の人が増えてしまったのです。非正規雇用者と正社員との賃金格差は次のようになります。
| 正規雇用者 | 非正規雇用者 |
| 給与(時給換算) | 給与(時給換算) |
| 1602円 | 1307円 |
この問題を解決するためには、非正規雇用者への待遇改善や、働き方改革のさらなる推進などが求められています。
▼参考
図表1-3-24 正規雇用労働者・非正規雇用労働者の賃金の推移(雇用形態別・時給(実質)ベース)
男女間の賃金格差が生じている
現代の日本においても、男女間の賃金格差は深刻な問題となっています。同じ仕事をしていても女性の賃金は男性の約3/4程度であるという問題があります。この状況によって男女間の経済的な格差を生み出し、経済活動への女性の参加意欲が失われてしまうかもしれません。
▼参考
一般労働者の月額賃金における男女格差が2年連続で縮小
高齢者の再就職が難しい
日本では、高齢者の再就職が難しいという現状があります。
この原因として、高齢者は年齢による体力の衰えやスキルの陳腐化などの問題が挙げられます。これらを克服するためには、定年後のキャリア形成やスキルアップに取り組むことが求められます。
企業側は高齢者の長年の経験や知識を活用した雇用を行うことができます。また、高齢者自身も、新たなスキル獲得や自己啓発に取り組むことで、再就職の道を広げることが可能です。
若者の働き方に対する意識が変化している
近年、若者の働き方に対する意識が大きく変化してきています。 以前は、「安定した生活」を求めて、一生務めることが前提の正社員として長時間労働をすることが当たり前でした。
しかし、現代の若者は「働きがい」や「自己実現」などを重視しています。ライフワークバランスを大切にし、自分自身の時間を確保しながら働きたいと考えているのです。
|
このような変化は、働き方改革や企業のSDGsへの取り組みに影響を与えています。企業も若者の意識に合わせた働き方改革を進め、SDGs達成に向けた取り組みを行う必要があるのです。
SDGs8を達成するための具体的な解決策4選
SDGs8を達成するための具体的な解決策を4つ紹介します。
企業が働き方改革を進める
企業が働き方改革を進めることは、SDGs8「働きがいも経済成長も」を達成するための重要なステップです。
最初に企業が取り組めることは、長時間労働の見直しです。残業時間の上限設定やフレックスタイム制度の導入などにより、健康的な働き方を促進し、労働者の生産性と幸福度を向上させることができます。
また、企業は定期的に社員の満足度調査を行い、働きがいを向上させる施策を検討することも大切です。
▼関連記事
《必見》SDGs8 働きがいも経済成長も|達成するために今から私たちにできること
非正規雇用者の待遇を改善する
非正規雇用者の待遇改善は、SDGs8達成への一歩として重要な課題です。非正規雇用者は、正規雇用者に比べて給与が低く、安定した雇用が保証されていないという現状があります。
企業は給与の公平性を保つために、同じ仕事をしている正規雇用者と非正規雇用者の給与格差を同一にすることが求められます。
また、非正規雇用者の社会保険の適用拡大や、働き方の自由度を高めるような取り組みも求められます。
男女平等を考慮した給与体系を見直す
日本では男女間での賃金格差が存在しています。
この課題への解決策として、役職や業績に応じた公平な給与体系を設けることが重要です。また、男女の役職や職種による賃金格差を是正し、同じ働きをした人には同じ給与を与えることが重要です。
さらに、男女それぞれのライフステージに応じた柔軟な働き方やキャリアパスを提供することで、長期的なキャリア形成をサポートし、賃金向上につなげることができます。
環境、社会、企業統治(ESG)を考慮した投資を行う
SDGs8の達成には、ESG投資を行うことも重要です。ESG投資とは、環境・社会・ガバナンスという3つの観点から企業を評価・分析して投資を行う手法のことを指しています。
ESG投資を行うメリットは主に2つあります。
|
ESG投資を行うことで、企業は環境に配慮した取り組みや、従業員の働きやすさを向上させる取り組みを行うことが求められます。その結果、企業の持続的な成長と、働きやすい環境の両方が実現しやすくなるのです。
SDGs8の達成につながる世界の国や国際機関の取り組み事例3選
SDGs8の達成につながる世界の国や団体の取り組み事例を3つ紹介します。
フィンランド|柔軟な働き方と学び続ける環境

フィンランドではSDGs8の達成に向け、働き方改革と教育の拡充に注力しています。
例えば、労働時間の調整を柔軟に行える制度を導入している企業が多くあり、16時を過ぎるとオフィスから人がいなくなることもよく見られる光景です。これにより、労働者は自身の生活スタイルや家庭の事情に応じた働き方を選択できます。
また、この取り組みは働きがいの向上だけでなく、生産性の向上にもつながるのです。
さらに、フィンランド人は仕事に就いた後も専門性を高めたり、新たな資格を取ったりする人が多いという特徴があります。これにより、就業機会の拡大やスキルアップを促進しています。
▼関連記事
SDGs目標8の取り組み|世界や日本、個人でできる取り組みまで網羅
▼参考
午後4時に仕事が終わる!? ――フィンランド人から学ぶ効率的で幸福な生き方
アメリカ|公正労働基準法の改正

アメリカではSDGs8の達成に向け、公正労働基準法の改正が進められています。この法律は、労働者の賃金や労働時間、労働環境について規定しており、主に低賃金労働者の待遇改善を目指しています。
例えば、時間外労働の規定が見直され、長時間労働による過重労働から解放されるようになりました。これによって、働きがいを感じられる環境が整いつつあります。
また、給与基準が一定額を下回る従業員が週40時間を超えて労働した場合、40時間を超える分の残業代を時給の1.5倍の額がもらえるようになりました。
IMF(国際通貨基金)|包摂的な景気回復に向けた取り組み
IMF(国際通貨基金)は労働市場の包摂性の向上に取り組んでおり、積極的な情報を発信しています。包摂性とは、いろいろな人が個性・特徴を認め合い、一緒に活動することを指しています。
IMFは男性と女性の間の「罪悪感の差」の調査を行い、その中で次の2つのことを明らかにしました。
・仕事と家庭の両立を支える態勢が整っていれば、コロナ禍で男性も女性も子どもをサポートし、負担を分担できた
・女性の雇用やキャリアを推進する上でワークライフバランスと男女格差の改善を促進する諸政策が不可欠になる
このような調査や情報発信を通して、働き方改革の推進に貢献しています。
▼参考
罪悪感、ジェンダー、包摂的な景気回復 日本に学ぶ教訓
SDGs8の達成につながる日本の政府や団体の取り組み事例4選
SDGs8の達成につながる日本の政府や団体の取り組み事例を3つ紹介します。
厚生労働省|すべての人が働きやすい環境づくり
厚生労働省は、全ての労働者が健康で安心して働ける環境を整備することを目指し、SDGs8の達成に取り組んでいます。
具体的な取り組みとして、多様な労働者(女性、高齢者、障がい者、外国人労働者など)が働きやすい職場環境の整備や、ワークライフバランスの推進、適正労働時間の確保などがあります。
また、労働者一人ひとりが能力を十分に発揮できるよう、キャリア形成支援や職業能力開発などの人材育成にも注力しています。
これらの取り組みを通じて、生産性向上と経済成長を図りつつ、持続可能な社会の実現に向けて前進しています。
▼関連記事
SDGs目標8の取り組み事例10選-現状や企業・個人にできることも紹介
第一生命HD|生命保険業界初の健康診断割引
画像引用:第一生命ホールディングス
例えば、毎年の健康診断の結果によって、保険料を割り引くシステムを設けています。これによって健康に気を使う動機付けを行いつつ、保険加入者自身の健康維持・向上に貢献しています。
また、歯の健康度によって保険料を割引する「認知症保険toスマイル」など、人々が健康に気を配るきっかけとなるような取り組みを積極的に行っています。
イケア・ジャパン株式会社|LGBTQ+の人々への支援
イケア・ジャパン株式会社は、社員のダイバーシティを尊重し、LGBTQ+の人々を含むすべての社員が働きやすい環境を作ることに取り組んでいます。例えば、性別や性的指向に関連する差別を排除し、職場でのハラスメント防止を積極的に推進しています。
また、同性パートナーに対する福利厚生の提供や、トランスジェンダーの社員が自分自身であることを尊重するための取り組みなど、LGBTQ+の人々への具体的な支援策を打ち出しています。
株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ・GU)|難民や社会的に弱い立場の人への支援
画像引用:グループ事業 | ファーストリテイリング
2025年までに100億円規模の社会貢献活動へ投資する目標を掲げ、難民や社会的に弱い立場にある人々への支援を行っています。
また、女性が活躍できるよう要職を担う人々の増加を促したり、次世代の経営者・リーダーの育成に力を入れたりするなど、社会課題の解決に向けた取り組みも積極的に進めています。
SDGs8を達成するために私たちにできること
これまで、日本政府や企業がSDGs目標8の達成に向けて取り組んでいる事例をご紹介してきました。ここでは、私たち一人ひとりが身近にできることについて紹介します。
まずは、SDGs目標8の現状について知ることが重要です。インターネットや新聞で、世界や日本の状況を調べてみましょう。私たちひとりひとりの行動を見直すきっかけになります。
他にも、フェアトレード商品を積極的に購入したり、SDGsの目標達成を目指して活動している団体に寄付したりするなど、できることはたくさんあります。
▼関連記事
コンビニ(セブン、ローソン)で買えるフェアトレード商品一覧-身近なイオンスーパー商品も紹介
まとめ
SDGs8では「働きがいも経済成長も」を目標にし、「労働」と「経済成長」の観点からより良い社会を目指しています。
この目標では、すべての人が働きがいを持って働ける社会を目指しています。しかし、小さい子どもが家計のために働いたり、職を得られない人がいたりと、さまざまな労働問題が生じています。
問題解決のためには、職場での環境づくりや働き方の多様性の尊重が大切です。また、私たちひとりひとりがフェアトレード商品の購入や労働問題への関心を高めることで、SDGs8の達成に貢献することができます。
大学では国際デザイン経営学科に所属し、解決が困難な問題をあらゆる角度から解決できるようにするため、日々勉学に努めている。