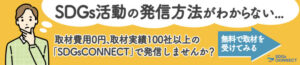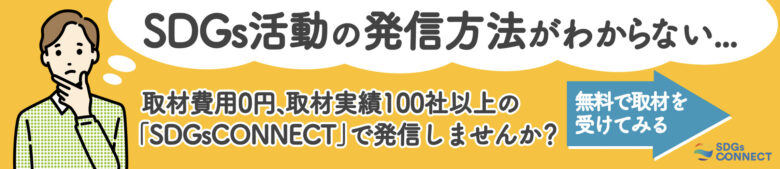【更新日:2023年10月19日 by 田所莉沙】
私たちは、自然からさまざまな恩恵を受けています。きれいな水や食料、そして酸素など、私たちの生活には欠かせないものです。
しかし、近年、私たち人間の活動によって、自然が破壊され、さまざまな環境問題が起きています。そして、そのような環境問題を食い止めることが求められています。
今回はSDGs15「陸の豊かさも守ろう」について、現状の課題や国内外の取り組み事例、私たちにできることまで分かりやすく紹介します。
| 【この記事で分かること】 |
見出し
SDGs 15「陸の豊かさも守ろう」とは|簡単に解説
SDGs15「陸の豊かさも守ろう」について内容や求められている理由、ターゲットを紹介します。
SDGs 15「陸の豊かさも守ろう」の内容
SDGs目標15「陸の豊かさを守ろう」は、陸に生息する動物や植物の保護や回復を目標としています。
世界では、人口増加や地球温暖化などにより、森林伐採や動植物の絶滅などの問題が生じています。そのため、SDGs目標15では、保護や回復に加えて、砂漠化の抑制や動植物の多様性の保全も掲げています。
陸上の豊かさと生物多様性を保つことで地球全体の生態系のバランスを保つと共に、人間に豊かな生活を提供し続けることを目標に設定しているのです。
▼関連記事
SDGs15「陸の豊かさを守ろう」の現状とは?|SDGs15への取り組み事例3選を紹介
なぜSDGs目標15が必要なのか
私たちの暮らしは、自然の恵みによって支えられています。住まい、食品、衣類、エネルギーなど、私たちが日常的に利用するものは、すべて自然から得られます。また、森林は、土砂崩れや洪水などの災害から私たちを守る役割も果たしています。
しかし、森林伐採や地球温暖化などにより、自然が破壊されつつあります。これによって、私たちの暮らしに以下のような影響が生じることが懸念されています。
|
SDGs目標15は、陸域生態系の保護と回復を目標としています。この目標を達成するためには、私たち一人ひとりが、自然を大切にする意識を持ち、行動することが重要です。
SDGs 15「陸の豊かさも守ろう」のターゲット
SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」には、以下の12個のターゲットが設定されています。
| 15.1 | ・2020年までに国際的な協定に基づいて、森林・湿地・山地・乾燥地など、陸の生態系と淡水地域の生態系によってもたらされる自然の恵みを守り、回復させる。 ・陸の生態系と淡水地域の生態系を持続可能な形で利用できるようにする。 |
| 15.2 | ・2020年までにあらゆる種類の森林の管理をすすめる。 ・2020年までに持続可能な森林の管理を行うことで、森林の減少をなくす。 ・おとろえてしまった森林を回復させ、世界全体において、植林を大きく増やす。 |
| 15.3 | ・2030年までに砂漠化対策を行う。 ・砂漠化、干ばつや洪水の影響を受けて衰えてしまった土地と土壌を回復させる。 ・これ以上世界各国で土地がおとろえないよう、努める。 |
| 15.4 | ・2030年までに持続可能な開発に必要となる山地の生態系を守る。 ・山地の生態系の能力を高め、さまざまな動植物が生きられる生態系を整える。 |
| 15.5 | ・天然の生息地がおとろえないようにし、生物の多様性が損なわれないようにする。 ・2020年までに絶滅危惧種として認定されている動植物の保護を行う。 ・絶滅してしまう可能性のある動植物に対し、絶滅しないための対策を実施する。 |
| 15.6 | ・国際的に決められたように、遺伝資源を使って得られる利益が平等に分けられるようにする。 ・遺伝資源を適切に使えるようにする。 |
| 15.7 | ・動植物の密猟や、法律に反した取引をなくす。 ・法律に反する野生生物の製品が求められたり、売られたりすることがなくなるようにする。 |
| 15.8 | ・2020年までに海外から移住してくる外来種の侵入を防ぐ。 ・外来種が自国の海や陸の生態系に与える影響を大きく減らす。 ・生態系に被害がおよばないように、優先度の高い外来種は駆除する。 |
| 15.9 | ・2020年までに生態系や生物の多様性を守ることへの大切さを考える。 ・国や地方の自治体などによる計画、開発のプロセスに組み込む。 ・貧困をなくすための取り組みやお金の使い方に組み込む。 |
| 15.a | ・生物の多様性や、生態系を守る。 ・生態系などを持続可能な形で利用できるようにする。 ・さまざまなところから資金を集め、より多くのお金が使えるようにする。 |
| 15.b | ・森林の保護や植林など、持続可能な森林の管理を行う。 ・あらゆるところから資金を調達し、発展途上国が持続可能な森林の管理を行えるようにする。 |
| 15.c | ・持続可能な形で収入が得られるように、コミュニティの能力を高める。 ・保護が必要な動植物に対する密猟や、法律に反する野生生物の取り引きをなくしていく。 ・密猟や違法な取引をやめるために、国際的な支援を強化する。 |
これらのターゲットは私たちが住む地球の陸地生態系を守ることを目指しています。この目指すべき方向性を理解し、私たち一人ひとりができることから始めてみましょう。
SDGs15に関する世界の現状と問題点
SDGs15に関する世界の現状と問題点を紹介します。
森林が減少し、環境問題を深刻化させている

世界では、森林の面積が減少しています。2020年には、世界全体の森林面積は約41億ヘクタールでしたが、これは世界全体の陸面積の31%に過ぎません。
特に、アフリカ大陸や南アメリカ大陸、東南アジアの国々で森林の減少が進んでいます。また、森林の面積が減少している国の多くは、近年経済が発展している国です。
森林の減少の原因は、人口増加と食料不足による森林の農地化・牧草地化です。人口増加に伴う食料不足を補うために、森林が農地や牧草地に転用されています。
森林の減少は、地球温暖化の促進や動植物の絶滅など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
▼関連記事
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」の取り組み内容とは?-取り組み事例5選を紹介
▼参考
世界の森林面積と森林率
生物が大量に絶滅する危険性がある
近年、地球温暖化や森林伐採などの影響により、世界中の動植物が絶滅の危機に直面しています。
国連の調査によると、現在、世界中の動植物のうち42,82種が絶滅の危険性があるとされています。絶滅危機種の数は、過去20年間で4倍近くであることがわかっています。
動植物の絶滅の原因は、地球温暖化による生息地の変化や、人による密猟・乱獲などが挙げられます。
動植物の絶滅を防ぐためには、密猟・乱獲を防いだり、地球温暖化を抑制したりすることが必要です。
▼参考
生物多様性の深刻な危機、絶滅危機種が4万種超に WWFと考える~SDGsの実践~【2】
農薬や化学肥料の使用、過度な農地利用などで土壌が劣化している
農薬や化学肥料の使い過ぎにより、土壌の豊かさが失われる恐れがあります。化学物質は、土壌生物に有害であり、土壌の生物多様性を低下させるのです。
さらに、過度に農地を利用することで、土壌の栄養素がなくなってしまい、土壌の豊かさを失う可能性があります。
したがって、化学肥料や農薬の使用は最小限にすることが必要です。また、持続可能な農業手法を導入することや、有機農業を取り入れることも検討してみてはいかがでしょうか。
砂漠化が進行している
SDGs15の問題の一つに、砂漠化があります。砂漠化とは、農地や森林の過度な利用や自然現象により、砂漠のような乾燥地帯に変わってしまう現象を指しています。
例えば、過度な放牧や灌漑農業による塩化、そして気候変動などが主な要因とされています。灌漑農業とは雨だけでなく、人工的な水路やため池などの用水を利用して収穫量を増やす農業のことを表しています。
このように、砂漠化には人間の活動が大きく影響していることが分かります。砂漠化が進行すると、地域の生態系だけでなく、食糧生産や生物多様性にも影響を及ぼします。
▼参考
農業の未来 メソポタミアの灌漑(かんがい)農業から未来都市(メトロポリス)のIT農業へ
SDGs15に関する日本の現状と問題点
SDGs15に関する日本の現状と問題点を紹介します。
放置される人工林が増えている

第二次世界大戦後、日本では森林伐採により山地が荒廃しました。その後、高度経済成長期には木材の需要が増加し、スギやヒノキなどの人工林が造林されています。現在、日本の国土面積の約7割は森林で、そのうち約4割は人工林です。
しかし、人工林は手入れが行き届かなくなると、土が痩せてしまい、根が雨水を吸い込めなくなるなどの問題が起こります。
さらに、近年は林業従事者の減少や安価な輸入木材の流入により、人工林の管理が行き届きにくくなっているのです。
▼関連記事
SDGs目標15の3つの課題-達成に向けた取り組みと私たちにできること-
絶滅危惧種の保護対策が進まず、外来種も生態系へ深刻な影響を与えている
日本では絶滅危惧種の保護対策が十分に進んでおらず、その一方で外来種の侵略が生態系に深刻な影響を与えています。環境省の調査によれば、絶滅危惧種は2017年時点で約3,772種に上ります。
さらに、外来種による影響も無視できません。ブラックバスやヒアリなど、生態系を乱す外来種が増加しています。
| 外来種 | 影響 |
| ブラックバス | 河川や湖沼の生態系を乱す |
| ヒアリ | 毒による人体への影響、生態系の乱れ |
このような現状を改善するためには、私たち一人ひとりが生物多様性に配慮した生活を心がけることが求められます。
▼参考
レッドリスト・レッドデータブック | 自然環境・生物多様性
建設ラッシュや都市開発で自然環境が失われている
近年、日本国内では急激な都市開発や建設ラッシュが進行しています。これらの開発は経済活動の活性化につながる一方で、自然環境の破壊も引き起こしています。
例えば、新たな住宅地や商業施設、工業団地などの開発によって森林や自然環境が大幅に減少しています。
また、開発により生息地を失う動植物も少なくありません。さらに、自然環境の喪失は地域の気候にも変化をもたらす可能性があります。
例えば次のような影響があります。
| 影響 | 詳細 |
| 生物多様性の喪失 | 自然環境の減少により、多種多様な生物が生息できる環境が失われる |
| 気候変動 | 森林が二酸化炭素を吸収する働きを持つため、その減少は地球温暖化の進行を加速する可能性がある |
| 地域の風土の喪失 | 自然環境が失われることで、地域固有の風土や文化が消失する恐れがある |
このように、建設ラッシュや都市開発はSDGs15の「陸の豊かさも守ろう」の目標達成にとって大きな障壁となっているのです。
地球温暖化により国内でも砂漠化が進む可能性がある
地球温暖化は日本国内にも深刻な影響を及ぼしています。特に、都市開発による緑地の減少と高温化によって土壌が乾燥しています。これにより、砂漠化が進行する可能性が指摘されています。
また、気温の上昇は農地の土壌にも影響を与え、水分が蒸発しやすくなるため、農地の砂漠化も問題となっています。
地球温暖化による国内の砂漠化は我々の生活環境だけでなく、食料を十分に育てることができなくなってしまうため、食物供給にも深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。
SDGs15に関する世界の取り組み事例
SDGs15に関する世界の取り組み事例を3つ紹介します。
DARWIN200 グローバル航海|若手環境保護活動家の育成

画像引用:DARWIN200
チャールズ・ダーウィンの研究に触発されて生まれた「DARWIN200 Global Voyage」は、世界中の若手環境保護活動家を育成するプロジェクトです。
選ばれた若手環境保護活動家は、ダーウィンが調査した動物や植物の個体数を調査し、絶滅の可能性などを評価します。また、現地の環境保護活動家と協力して、保護活動の改善に取り組みます。
このプロジェクトを通じて、若い環境保護活動家は自然保護の調査能力や戦略を学び、各国の環境保護に貢献することが期待されています。
▼関連記事
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」|世界の取り組み事例5選
世界自然保護基金(WWF)|野生生物の保護に貢献

画像引用:WWF
世界自然保護基金(WWF)は、世界100か国以上で活動する環境保全団体です。1961年にスイスで設立され、世界各国で動植物の多様性の回復や地球温暖化の防止、脱炭素社会の実現などを目指しています。
WWFの活動テーマは4つあり、その1つが「野生生物を守る」ことです。世界各地で動植物が絶滅の危機に瀕しており、WWFは密猟・密輸の防止や生態系の保全など、さまざまな取り組みを通じて野生生物の保護に取り組んでいます。
WWFは国際自然保護連合(IUCN)と共同で、野生生物の国際取引を監視する「トラフィック・ネットワーク」を運営しています。トラフィック・ネットワークは、野生生物の過剰な取引や密猟・密輸を防ぐための活動を行っています。
また、WWFは地域の生態系のバランスが崩れないように、生態系の保全にも取り組んでいます。
国際連合開発計画(UNDP)|農村の開発や生物多様性の維持

画像引用:国連のUNDPってどんな組織?
国際連合開発計画(UNDP)は、持続可能な社会の実現に向けて、貧困や不平等の解消などさまざまな取り組みを行っている国際連合の機関です。
SDGs目標15に関連する取り組みとして、農村の開発や生物多様性の維持を目指した農業方法への転換など、持続可能な農業の促進を目的とした「グリーン・コモディティ・プログラム」を実施しています。
このプログラムは2009年から実施しているプログラムで、農村開発に関する人材を育成することで持続可能な農業を目指しています。また、労働環境が問題となっているコーヒーやココア、牛肉などの生産過程の改善に力を入れています。
SDGs15に関する日本の取り組み事例|企業の取り組み事例3選
SDGs15に関する日本の取り組み事例を3つ紹介します。
大和ハウス|桜の保全活動

画像引用:大和ハウス工業株式会社
大和ハウス工業株式会社は、自然と共生するまちづくりを目指す企業です。SDGs目標15の達成に向けて「Daiwa Sakura Aid」という取り組みを行っています。
この取り組みでは、公益財団法人吉野山保勝会と共同で、吉野山でシロヤマザクラを種から育てています。また、森林の保全活動では、伐採した木材を再利用することで、森林の再生に貢献しています。
これらの取り組みを通じて、大和ハウス工業は、自然と共生する持続可能な社会の実現に貢献しています。
UNIQLO|服のリサイクル・リユース
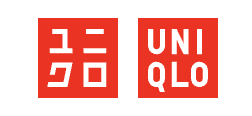
画像引用:UNIQLO
UNIQLOは、SDGs目標15の達成に向けて、服のリサイクル・リユースに取り組んでいます。この活動は「RE. UNIQLO」と呼ばれ、UNIQLOが提供している全商品を対象としています。
リサイクル・リユースされた衣類は、難民の人々への衣料支援や、二酸化炭素排出量の削減に役立てられています。
リサイクル・リユースを行うための衣類は、UNIQLOの店舗に設置されているRE. UNIQLO回収ボックスで回収しています。UNIQLO以外のブランドの衣類も回収対象です。
着なくなった服がある方は、ぜひこの活動に参加してみてください。
三井物産|持続可能な森林モデル

画像引用:三井物産
森林経営を民間企業にとっても持続可能とするために、三井物産は「持続可能な森林モデル」を推進しています。
このモデルでは、適切な経営・管理によって森林の多様な価値・機能を高め、そこからもたらされる収益を森林経営に循環させていきます。
三井物産は、社有林でのモデルの実現に加え、他の森林保有者・管理者の皆様にもモデルを提供することで、森林経営の持続可能性を高め、脱炭素社会の実現に貢献していきます。
▼参考
三井物産の森について
SDGs 15のために私たちにできること5選|小学生・中学生にもおすすめ
SDGs 15のために誰でも取り組めることを5つ紹介します。
日常生活で地球環境に配慮した行動を心がける

SDGs 15の目標に共感し、自分たちでも何か行動を起こしたいと考える方も多いでしょう。
まずは、何気ない日常の中で地球にやさしい選択をするように心がけましょう。例えば、エコバッグの利用や節水・節電、リサイクル製品の利用などが挙げられます。これらの小さな行動が積み重なることで、大きな影響を与えることができます。
また、自然を身近に感じる機会を持つことも大切です。公園や森林で過ごす時間を持つことで、自然環境を守る意識をより深めることができます。
さらに、食事にも目を向けてみてください。食材の選び方1つでも地球環境に影響します。旬の食材を選ぶことや地元産の食材を選ぶことなどにも注意することが大切です。
▼関連記事
SDGs目標15「森の豊かさも守ろう」私たちにできること
SDGs 15に対する情報を取得し、発信する
SDGs 15について行動しようと思ったら、まずは情報を得ることが大切です。日本や世界の現状を知り、何が求められているのかを理解することが求められます。
さらに、調べて得た情報を他の人に伝えることも重要です。例えば、家族や友人などの身近な人に話をして、周りの人から行動を変えていくことができます。
まずはSDGs 15について関心を持ち、調べてみてはいかがでしょうか。
環境に配慮した商品やサービスを選んで購入する
FSCマークのついた製品を選ぶことで、森林の保護に貢献できます。
FSCマークとは、森林の持続可能な管理を推進する団体であるFSC(Forest Stewardship Council)によって認定された製品に付けられるマークです。
FSCマークのついた製品を選ぶことで、以下の2つのことに貢献できます。
|
FSCマークのついた製品は、身近なスーパーやコンビニでも購入できます。例えば、紙パックや紙袋、紙ストローなどです。
ペットボトルではなく紙パックのジュースを購入する、プラスチックストローではなく紙ストローを使うようにするなど、小さなことから始めてみましょう。
地域の自然保護活動や清掃活動に参加する
地元の自然保護活動や清掃活動に参加することは、SDGs 15の目標達成に貢献する方法の1つです。例えば、公園や川辺の清掃、植樹活動、外来種の除去といった活動があります。
| 活動 | 内容 |
| 公園の清掃 | 公園内のゴミ拾いや設備のメンテナンス |
| 植樹活動 | 新しい植物を植え、森林の再生を助ける |
| 外来種除去 | 生態系のバランスを保つため、外来種を取り除く |
さらに、これらの活動に参加することで参加者自身も自然と触れ合う機会を得られ、自然保護の大切さを肌で感じることができます。
活動に参加することで、地球環境の保全を身近なところから始められます。ぜひ、ご自身の地域で行われている活動に参加してみてください。
環境問題に取り組むNGOやNPOへ寄付をやボランティアをする
環境保全団体への寄付で、気軽にSDGs目標15に貢献できます。
SDGs15達成のために、私たちひとりひとりにできることはたくさんあります。しかし、自らの意志で行動を起こすことが難しい場合もあります。
そのような人におすすめの取り組みが、環境保全団体への寄付です。環境保全団体は、私たちの代わりに森林保護や土壌保全などの活動を行っています。
寄付をすることで、これらの活動を支え、SDGs目標15の達成に貢献することができます。
寄付先として、以下の団体が挙げられます。
|
これらの団体は、それぞれに得意分野や活動内容が異なります。自分の関心や活動したい内容に合わせて、寄付先を選ぶとよいでしょう。
環境保全団体への寄付は、SDGs目標15を達成するために、私たちができる最も簡単な方法のひとつです。ぜひ、気軽に取り組んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」は、森林の減少や動植物の絶滅を防ぐなど、自然の保護や回復を目指した目標です。
私たちの生活は自然の恵みによって成り立っており、豊かな自然が失われれば資源不足や食料不足などによって私たちの生活も困難となります。
企業や政府・自治体の取り組みだけではなく、私たちにもできることを5つ紹介しました。まずは、簡単にできることから始めてみてはいかがでしょうか。
大学では国際デザイン経営学科に所属し、解決が困難な問題をあらゆる角度から解決できるようにするため、日々勉学に努めている。