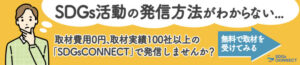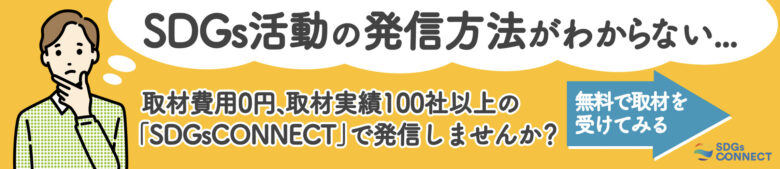【更新日:2022年9月19日 by ナオ】
SDGsが世界中で取り組まれていますが、それと同時にSDGsの矛盾を指摘する声も上がっています。
実際どんな矛盾が生じているのか。本当に達成できるのか。本当に必要なのか。などさまざまな疑問があると思います。
今回の記事では、そんな矛盾とどう向き合いながら行動していくべきかについて解説していきます。
見出し
SDGsの取り組みに矛盾が生じる理由
SDGsの取り組みに矛盾が生じ、世間から指摘されてしまうことも少なくありません。
ではそもそもなぜSDGsの取り組みに矛盾が生じてしまうのでしょうか。
大きく3つの理由を紹介します。
資本主義や経済成長との矛盾

17個あるSDGsの目標の一つに、目標13「気候変動に具体的な対策を」というゴールがあります。
これは地球温暖化などによる気候変動を解決するための具体策を提案し、行動していくというものです。
したがってSDGsでは二酸化炭素の削減を目指しています。
しかしSDGsでは目標8として「働きがいも経済成長も」というゴールも掲げられています。
経済成長の実現には、高確率で二酸化炭素の排出が伴ってしまうことは、容易に想像できるでしょう。
太陽光パネルや電気自動車の開発なども事例の一つです。
そのためSDGsで環境保全と経済成長の両軸をゴールに掲げていることから「矛盾している」と指摘されてしまう現状があるのです。
また、多くの国が経済成長を追い求めている背景には「資本主義」があります。
資本主義の社会では自由な競争が発生するために、経済が発展します。
経済成長を追い求めるシステムである資本主義では、永遠に二酸化炭素の削減や環境保全が達成されないのではと疑念を抱かれ、SDGsが矛盾していると指摘されてしまうのです。
個人でSDGsに取り組むときの矛盾
SDGsの取り組みを行うにあたり、「個人で行うSDGsの取り組みと、SDGsの取り組みを行っている個人が大切にしている軸の間でずれが生じた状態」が発生するとSDgsに矛盾が起きていると指摘されてします。
たとえば、小食の人が食事を注文して、食べきれない量を残すことはフードロスに繋がります。しかし、小食の人に無理やりにでもすべて食べさせることが正しいとは言えません。
個人でSDGsに取り組んだ際に矛盾が生じる可能性もあるのです。
企業でSDGsに取り組むときの矛盾(SDGsウォッシュ)
企業が取り組むSDGsには、時として矛盾が存在します。
個人で取り組むSDGsと違い、よい面でも悪い面でも世間に大きな影響を及ぼすのが企業によるSDGsの取り組みです。
そのためSDGsの取り組みに慎重になる必要性があります。しかしSDGsへの取り組みを行っているように見えて、その実態が伴っていないビジネスも存在しているのです。
そのようなビジネスを「SDGsウォッシュ」と呼びます。
こちらの記事でSDGsウォッシュと指摘された企業例や、避ける方法についてを詳しく紹介しています。
▽SDGsウォッシュを詳しく知りたい方はこちら
▶関連記事|《徹底解説》SDGsウォッシュとは?3つの事例や気をつけるべきポイントを紹介>>
SDGsと矛盾している4つの問題
SDGsに矛盾が発生してしまう理由を理解できたかと思います。
では具体的にはどのような矛盾が世の中では発生してしまっているのでしょうか。
ここではSDGsに関する矛盾の事例を4つ紹介します。
例1|電気自動車の二酸化炭素排出問題

環境にやさしいと言われており、現在も開発が進んでいる電気自動車は、エネルギー源である電気に注目すると、違った捉え方ができます。
日本をはじめとした世界の産業主要国は、火力発電に頼っている国が多く、日本原子力文化財団が公表した2019年のデータでは、日本は89%、中国は87%、アメリカは84%、火力発電に頼っているのです。
つまり、電気自動車は既存の車よりも排気ガスを減らせるとしても、燃料の代わりにエネルギー源としている電気の発電を必要としているために、膨大な二酸化炭素が空気中に排出されてしまうという問題が発生します。
例2|プラスチック削減による雇用問題
現在、プラスチックの削減が叫ばれており、ラベルレスのペットボトルが普及したり、紙ストローを採用する飲食店が増えたりするなどの取り組みが行なわれています。
しかし、プラスチックの削減をこのまま続けると、プラスチックを作っている人たちの仕事が失われ、SDGs目標8の「働きがいも 経済成長も」に相反する動きとなってしまう恐れがあることも事実です。
また、ラベルレスの普及により商品の形が似てしまい、他社との区別が難しくなるという問題も発生しています。
独自の形のペットボトルを作れる大企業と違い、中小企業は開発力が低く、差別化が図れずに大きく売り上げに響く可能性も懸念されています。
例3|高価なオーガニック化粧品
ナチュラルコスメブランド「LUSH」をはじめとした、環境に配慮した成分配合や、サステナブルなパッケージを使用している化粧品が存在します。
しかしそのような商品は一般的な化粧品と比べて値段が高いことも多く、手を出しにくい人が一定数存在するのも事実です。
SDGsを追求した商品が開発されても、値段が高いという理由から購入を諦めなければいけないという矛盾が存在していると考えられます。
例4|オリンピックの廃棄問題
オリンピックは「スポーツは持続可能な開発における重要な鍵」とされており、政府は気候変動対策や資源の有効利用、生物多様性の保全などに配慮することを運営の柱にしていました。
しかし、国立競技場の建設において貴重な熱帯林の木材が資材として使われていたことや、スタッフ向けに配られる予定だった弁当が大量に廃棄されてしまったことなど、実際はSDGsに矛盾した事例も存在していたことが判明しています。
矛盾を回避するために行なうべき2つのこと
では、SDGsの矛盾を防ぐためにはどのような対策が必要でしょうか。いくつかの対策をご紹介いたします。
1.SDGsという名前に囚われず、本質を見抜く

SDGsの矛盾を防ぐためには、SDGsの枠に囚われず、課題の本質を見抜いていくことが大切です。
SDGsウォッシュなど、SDGsに取り組んでいるように見せて、実際には根本的な解決にはつながっていないという事例は少なくありません。
たとえば、リサイクルされた原料を使っている製品だからと言って、それだけでSDGsを達成することにつながるのでしょうか。
もしその製品を大量生産・大量消費しているならば、それは課題の根本的な解決にはなっていないと言えます。
目の前にある課題をただ解決するのではなく、「そもそもこの課題はなぜ発生しているのか」「表面化されている課題を解決するだけで、本当に課題を解決することにつながるのか」など、一歩先の視点を持つことで、課題の本質を理解でき、矛盾を防げるでしょう。
2.他人に押し付けない
個人としては、自分では絶対に譲れない軸を持ちながら、できる範囲でSDGsに向けて取り組んでいくことが大切です。
自分の許容範囲以上の活動を続けていると、長く続かなかったり、途中で嫌になってしまったりすることがあります。
よって、「自分だけが無理する必要はない」という心を持ちながら、個人でSDGsの取り組みを行っていくことが鍵となるのではないかと考えています。
その上で、他人にも自分の軸としていることがあることを忘れてはいけません。
そのため、自分の行っているSDGsの取り組みを他人に押し付けるといった行動は推奨できません。自分のできる範囲で、少しずつでも長く続けていくことが大切であると言えるでしょう。
結局SDGsに取り組むことはメリットになるのか
さまざまな矛盾が発生する可能性のあるSDGsですが、果たしてそこまでしてSDGsに取り組む理由や意義はあるのでしょうか。
SDGsに取り組むメリットは企業にとっても個人にとっても多くあります。
ここでは代表的なメリットを3つ紹介します。
メリット1|環境問題の解決に近づく

1つ目は、環境問題の解決に近づくことです。
よく「個人でSDGsに取り組んでも何も意味がない」という意見を見かけます。
しかし、実は日本の二酸化炭素排出量の14.6%を「家庭部門」が占めていることをご存じでしょうか。
環境問題を解決するためにも個人でSDGsに取り組むことは必要不可欠です。
また環境問題を解決することで、気候変動など私たちの生活に関する事象も付随的に解決することになります。
SDGsに取り組むことで個人にとってはもちろん、地球全体に対してもメリットがもたらされるのです。
メリット2|コスト・支出の削減できる
メリットの2つ目はコスト・支出の削減につながる点です。
個人で取り組むSDGsとして節電・節水、エコバッグの利用などがあげられます。
これらに取り組むことで支出を抑えられるため、メリットは充分にあるでしょう。
また最近ではLoopというサービスも話題を呼んでいます。
Loopとは、アメリカのベンチャー企業が始めたサービスです。
再利用可能な容器ボトルを用いてECや小売店で販売し、使用後に容器ボトルを回収、洗浄、再充填の後に再販売することでごみを減らすシステムになっています。
この容器ボトルを返却することで、購入時に支払った容器代がアプリ経由で返金される仕組みになっているため、支出を気にせずSDGsに貢献できるのです。
このように費用の面でもSDGsに取り組むことで得られるメリットは多くあります。
メリット3|将来の世代によりよい世界を残す
メリットの3つ目は自分の子どもや孫など、将来の世代にとってよりよい社会を残せることです。
突然ですが、化石燃料の可採年数(※)をご存じでしょうか?
※可採年数:現在採掘可能とされている埋蔵量を、年間生産量で割った数値のこと。
石炭は約118年、ウランは約106年、天然ガスは約59年、石油は約46年となっています。
可採年数からもわかるように、このままSDGsおよび世界の課題を解決する姿勢が見えなければ、まさしく「持続可能ではない社会」ができてしまうのです。
自分の子どもや孫など、次世代が過ごしていく世界を少しでもよいものにするためには、SDGsの考え方を持つこと自体が一番重要になります。
この先の未来が明るいものになることがSDGsに取り組むことで得られる、1番のメリットではないでしょうか。
▽SDGsがもたらすメリットについて詳しく知りたい方はこちら
▶関連記事|SDGsがもたらすメリットとは?企業・個人が得られるメリットを紹介>>
SDGsの達成状況

昨今さまざまな場所でSDGsが取り組まれていますが、実際SDGsはどの程度達成されているのでしょうか?
こちらの記事には日本のSDGsの現状が詳しく載っています。
現時点で何が達成されていて、何が達成されていないのか。日本のSDGsの本質的な課題を見つけるためにも、ぜひ一度ご覧ください。
▽日本のSDGsの現状について詳しく知りたい方はこちら
▶関連記事|SDGsの日本の現状2021|コロナが与えたSDGsへの影響とは>>
まとめ
個人と企業の両方の点で、一見SDGsの取り組みを行っているように見えても、実は矛盾していて、逆効果をもたらしている事例もあることが分かったかと思います。
私たちはSDGsをただ行うだけで終わりにするのではなく、定期的に行動を振り返り、自分の活動がSDGsに矛盾していないかを振り返る必要があります。この記事が、自分の活動を思い返すきっかけになれば幸いです。
わたしたちのメディアはSDGsに特化したメディアです。さまざまなトピックスが取り上げられており、新たな発見があるかもしれませんので、ぜひ読んでみてください!
大学では西洋史を勉強しています。趣味はトマトの食べ比べ。高校時代から触れてきたSDGsについて、自分自身でも学びながら発信していきます!